-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年1月 日 月 火 水 木 金 土 « 8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
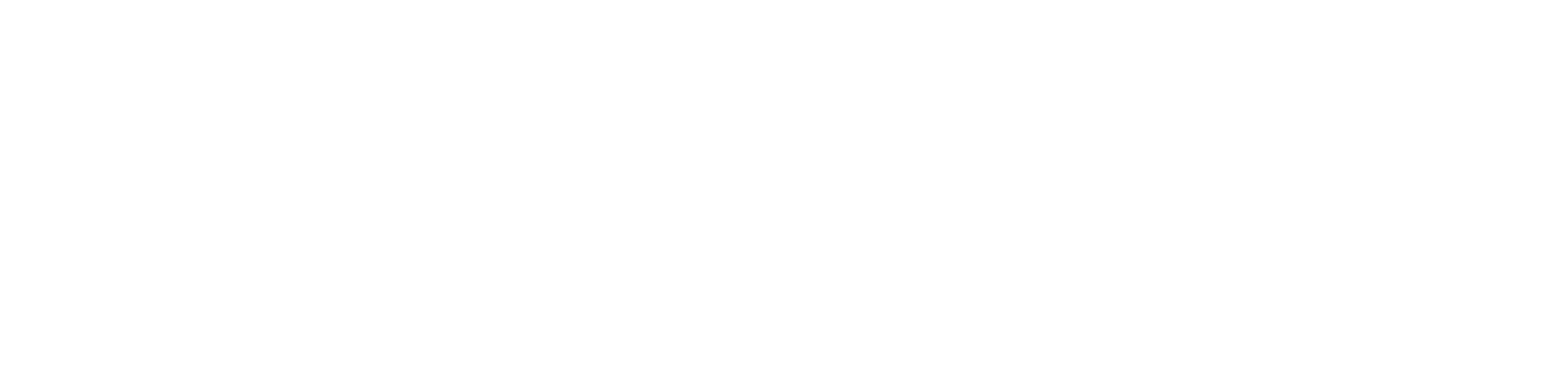
皆さんこんにちは!
埼玉県比企郡小川町を拠点に関東圏内の建設現場での鉄骨工事一式を行っている
有限会社須永鉄建、更新担当の富山です。
工場で仕上げられた鉄骨が現場に搬入されると、いよいよ「クレーン作業」が始まります。
数トンの鉄骨を宙に舞い上げ、建物の骨組みが立ち上がる光景は壮観で、鉄骨工事の象徴的な瞬間です。
玉掛け(たまがけ)
鉄骨にワイヤーをかけ、重心を見極めて吊り上げ準備をします。
バランスが崩れると鉄骨が回転・落下する危険があるため、国家資格「玉掛け技能士」が必ず担当します。
吊り上げ
クレーンオペレーターが操作し、鉄骨を空中に持ち上げます。
数トンの部材を揺らさずに狙った位置まで運ぶ技術は熟練のなせる業です。
据え付け
高所で待機する「鉄骨鳶」が鉄骨を受け止め、仮ボルトで素早く固定します。数十メートルの高さでの作業は一瞬の気の緩みも許されません。
吊り荷の下には人を入れない
基本中の基本であり、常に声掛けや誘導で徹底。
天候チェック
特に強風は大敵。風速が基準を超えると作業は即中止。
合図の統一
クレーンオペレーターと地上スタッフが無線・手旗で連携。誤解を防ぐためにシンプルで明確な合図を使います。
近年の鉄骨工事では、ICTや最新機械を活用した安全・効率化が進んでいます。
GPS付きクレーン … 部材の位置を正確に把握できる。
施工シミュレーション … 3Dモデルで吊り上げ順序を事前に確認。
大型クレーン … 超高層ビルや大規模物流施設にも対応可能。
クレーンで吊り上げられた鉄骨が次々と組み上がり、建物が一気に形を現す瞬間。
現場の誰もが息をのむ迫力です。
この作業を支えるのは、
高所で奮闘する鉄骨鳶、
安全を守る玉掛け技能士、
操縦桿を握るクレーンオペレーター。
三者が阿吽の呼吸で動くことで、迫力と安全を両立させた鉄骨工事が成り立っています。
👉 クレーン作業は「鉄骨工事の花形」。
街のシンボルとなる大規模建築が空へと伸びていくダイナミックな瞬間を担う、まさに現場の要です。
次回もお楽しみに!
埼玉県比企郡小川町を拠点に関東圏内の建設現場での鉄骨工事一式を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県比企郡小川町を拠点に関東圏内の建設現場での鉄骨工事一式を行っている
有限会社須永鉄建、更新担当の富山です。
鉄骨工事は現場での組立作業が目立ちますが、実際には「工場での鉄骨加工」が最初の要であり、この工程がすべての基盤を作ります。
工場での精度がわずかでも狂えば、現場での組立がスムーズに進まず、最悪の場合は建物全体の安全性を損なう恐れすらあるのです。
切断作業
長尺の鋼材を設計図に基づいて正確な長さに切断します。
ガス切断機やレーザー切断機を使い、誤差はミリ単位。ここでの精度が、後の組立に大きく影響します。
穴あけ作業
高力ボルトを通す穴を開ける工程。位置が1ミリでもずれればボルトが入らず、現場で作業が止まってしまいます。NC(数値制御)加工機による自動化で、常に正確な位置に穴をあけていきます。
溶接作業
部材を強固に接合するための作業です。アーク溶接や半自動溶接機、さらにはロボット溶接を活用。品質にムラが出ないよう、最終チェックは必ず熟練の溶接工が担当します。
組立・仮組み作業
工場内であらかじめ柱や梁などを組み合わせ、現場でそのまま据え付けられるように仕上げます。これにより現場の効率が大幅に向上し、安全性も確保されます。
工場には「鉄骨製作管理技術者」や「溶接管理技術者」が常駐し、各工程を厳しく監督しています。
溶接部の超音波探傷検査(UT)や磁粉探傷検査(MT)で内部の欠陥をチェック。
製作記録や証明書を発行し、設計者や監理者に提出。
部材ごとに製作番号を付与し、現場で迷わず組み立てられるように管理。
鉄は水や空気に触れるとすぐに錆びます。
そこで工場段階で以下の処理を行います。
ショットブラスト処理 … 鋼材表面を研磨し、塗装の密着性を高める。
防錆塗装 … 下塗り・中塗り・上塗りの三層でしっかりガード。
溶融亜鉛メッキ … 厚い亜鉛膜で覆い、数十年単位で錆を防ぐ。
👉 鉄骨加工は、現場に届いた時点で「建物の半分が完成している」と言われるほど大切な工程です。
ここでの正確さと丁寧さが、街にそびえる大きな建物の安全と美しさを支えています。
次回もお楽しみに!
埼玉県比企郡小川町を拠点に関東圏内の建設現場での鉄骨工事一式を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県比企郡小川町を拠点に関東圏内の建設現場での鉄骨工事一式を行っている
有限会社須永鉄建、更新担当の富山です。
今回は「鉄骨工事の魅力」について、実際の作業現場や職人の視点からじっくりご紹介します。
鉄骨工事の魅力は、ひとことで言えば「男らしさと繊細さの両立」。
力強さだけでなく、知識・技術・集中力が求められるプロフェッショナルの仕事です。
鉄骨工事の最大の魅力の一つは、スケールの大きな建築に関われることです。
私たちが手がける現場の多くは:
高層ビル
大型ショッピングモール
工場や物流センター
学校や公共施設
普段街を歩いていて見かける「立派な建物」の裏側には、必ず鉄骨工の存在があります。
自分の仕事が、社会インフラや経済活動を支えているという実感を持てるのは、大きなモチベーションになります。
鉄骨工事の現場では、最新の施工技術や機械が導入され続けています。
高精度な溶接技術(半自動・アーク溶接など)
高所作業車・足場不要の安全機材
3D CADやBIMによる設計との連携
鉄骨建方の自動化・省力化
こうした先進技術に触れられる環境で、常にスキルアップを図れるのも鉄骨職人としての魅力です。
資格を取得すれば、施工管理や図面作成、独立といったキャリアアップの道も広がっていきます。
鉄骨工事は一人では完結しません。
玉掛け、クレーン、溶接、ボルト締め、設計……すべての工程が連携しながら進むため、現場では仲間との信頼関係が何より大切です。
「次、そっち持ち上げるよ!」「締め込み確認した?」
そんな声が飛び交う中、言葉にならない一体感で動いていくのが、鉄骨工事の現場です。
厳しい中でも笑い合える、気持ちを通わせる――そうした“現場の絆”も、鉄骨工の魅力のひとつです。
何もない更地から、どんどん柱が立ち、梁がつながり、フロアが重なっていく――
まるで“街を組み立てる”ような、そんなスケールの大きさが味わえるのは、鉄骨工ならではの醍醐味です。
完成したときの景色は、まるで一つの芸術作品のよう。
その中に自分の汗と技術が詰まっていると感じた瞬間、仕事への誇りと充実感がこみ上げてきます。
鉄骨工事は、体力も精神力も鍛えられる仕事です。
だからこそ、「続けてきて良かった」「この仕事が自分を変えた」と感じる職人も少なくありません。
毎日身体を動かす → 健康的
責任ある作業を担う → 精神的に成長
チームの一員として動く → 協調性・判断力が養われる
ただの“力仕事”では終わらない。
人間力そのものを磨ける現場が、鉄骨工事には広がっています。
鉄骨工事は、建築の「骨格」を担う仕事です。
見えない部分でありながら、建物全体の安全性・耐震性・長寿命化に深く関わっています。
そしてその仕事の先には、人々の暮らし、街の景観、次の世代の社会が待っています。
「自分の手で未来をつくっている」
そう胸を張って言える職業、それが鉄骨工事の世界です。
次回もお楽しみに!
埼玉県比企郡小川町を拠点に関東圏内の建設現場での鉄骨工事一式を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県比企郡小川町を拠点に関東圏内の建設現場での鉄骨工事一式を行っている
有限会社須永鉄建、更新担当の富山です。
今回は「鉄骨工事のやりがい」についてお話しします。
鉄骨工事と聞いて、皆さんはどんな仕事を思い浮かべますか?
大きな建物を支える「骨組み」を組み上げるダイナミックな作業、クレーンや高所作業の緊張感、溶接の火花――そんな力強い現場のイメージがあるかもしれません。
でも実は、この仕事には“力仕事”以上の深い満足感、職人としての誇り、そして社会とのつながりが詰まっています。
鉄骨工事とは、建物の骨格となる鋼材(H形鋼、角形鋼管など)を組み立て、接合し、建物全体を構造的に支えるための工事です。
ビルや工場、商業施設、体育館、橋梁、高層マンションなど、規模の大きな建築物には必ずと言っていいほど鉄骨が使われます。
私たち鉄骨工が扱う材料は、数百kgから数トンの鋼材。これを設計図通りに正確に配置し、建物の構造体を一から組み立てていきます。
完成後には見えない部分かもしれませんが、その**一つひとつが建物を支える「命綱」**です。
「この建物の骨格は、俺たちが組んだ」
そんな実感が残る仕事に関われるのは、何物にも代えがたいやりがいです。
鉄骨工事は、「紙の上の設計図」から「現実の構造物」へと変わる瞬間を間近で体験できる仕事です。
図面を読み取り、現場で微調整しながら、巨大な鋼材を次々と立ち上げていく――まるでパズルを完成させるような緻密さと、ダイナミックな施工の融合がそこにあります。
クレーンオペレーターとの連携、溶接工・鍛冶工との共同作業、現場管理者との打ち合わせなど、チームで一つの大きな建築を作り上げる一体感もまた、この仕事ならではのやりがいです。
鉄骨工の象徴ともいえるのが「高所作業」。
数十メートルの高さで、細い梁の上を渡り歩き、鋼材をボルトや溶接で組み上げる仕事には、一瞬の気の緩みも許されない緊張感があります。
しかし、この命がけの現場だからこそ、安全管理の徹底・仲間との信頼関係・仕事への集中力といった、現場でしか得られない価値が生まれます。
「今日は何事もなく終わった」「無事に1フロア組み終えた」
その毎日の達成感が、やりがいにつながっていくのです。
鉄骨工の仕事は、10年、20年、それ以上の時を超えて、街の中で“残り続ける仕事”です。
完成後の建物を見上げたとき、「この骨組みは俺たちがつくった」と言える誇りは、何年経っても色あせません。
自分の子どもや孫に、「あのビル、パパが建てたんだよ」と胸を張って言える――
それが、この仕事最大のやりがいかもしれません。
次回もお楽しみに!
埼玉県比企郡小川町を拠点に関東圏内の建設現場での鉄骨工事一式を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県比企郡小川町を拠点に関東圏内の建設現場での鉄骨工事一式を行っている
有限会社須永鉄建、更新担当の富山です。
今回は「鉄骨工事の未来」についてご紹介します。
現代建築に不可欠な鉄骨構造ですが、テクノロジーの進化と社会ニーズの変化によって、鉄骨工事そのもののあり方も急激に変わりつつあります。
この回では、次世代の鉄骨工事を支える“技術”“施工方法”“人材”の3つの視点から、未来像を描いてみましょう。
すでに建築業界では一般化しつつある「BIM(Building Information Modeling)」ですが、鉄骨工事においてもその活用が進んでいます。
詳細な鉄骨フレームの3D設計と干渉チェック
プレカット図面の自動生成と工場製作の効率化
部材の搬入・組立計画の最適化
これにより、無駄な資材の発注ミスや、現場での加工ミスを大幅に削減できるようになっています。
今後の鉄骨工事で注目されるのが「自動化」です。特に鉄骨のボルト締結や塗装、溶接といった反復作業では、ロボット導入が始まりつつあります。
自走式ボルト締結ロボット
ドローンを用いた高所点検・寸法測定
溶接アームの工場内全自動化
これらは労働力不足への対策としても非常に有効であり、熟練技術の継承と生産性の両立を図るカギとなるでしょう。
未来の鉄骨には、さらなる機能性も求められています。
耐火性を高めた複合鋼材
断熱・遮音性能を持つ被覆鉄骨
軽量かつ高強度な新合金鋼
こうした次世代材料の実用化が進むことで、より高性能な建築物の設計が可能になります。また、部材の軽量化は施工負担や輸送コストの軽減にも直結します。
どんなに技術が進化しても、それを活かす“人”がいなければ鉄骨工事は成り立ちません。
若手向けの実践教育(VR訓練、CAD研修)
ベテランの技術ノウハウのマニュアル化
外国人技能実習生との共存と育成制度の整備
未来を見据えた職人育成は、技術力だけでなく現場力・コミュニケーション力・安全意識の総合力を育むものです。
鉄骨工事の未来は、単なる“鉄を組む作業”から、“テクノロジーと人を組み合わせて都市を形づくる仕事”へと大きくシフトしています。
持続可能性・効率性・安全性——そのすべてを同時に満たすには、業界全体が連携し、次世代の工法と人材を育てていく必要があります。
「鉄と未来をつなぐのは、私たち現場の手である」
そんな誇りを胸に、これからの時代にふさわしい鉄骨工事を共に創っていきましょう。
次回もお楽しみに!
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県比企郡小川町を拠点に関東圏内の建設現場での鉄骨工事一式を行っている
有限会社須永鉄建、更新担当の富山です。
今回は、鉄骨工事が環境に与える影響と、それに対する業界の取り組みについて深掘りしていきます。
鉄骨工事といえば、高層ビルや工場、橋梁などあらゆる大型構造物に関わる重要な工事分野です。しかしその一方で、資源・エネルギーの大量消費や産業廃棄物の発生といった環境問題とも隣り合わせであることはあまり知られていません。
まず注目すべきは、鉄骨の製造段階におけるCO₂排出量です。鉄鋼はその生成過程で多量のエネルギーを要するため、製造時の温室効果ガス排出が極めて多い素材として知られています。
具体的には、1トンの鋼材を生産する際に約2トンのCO₂が発生するといわれています。
このような背景から、建物の構造に鉄骨を採用することは、設計段階から「環境負荷」を前提に考える必要があるのです。
製造だけでなく、現場施工においても環境リスクは存在します。
ガス溶接・溶断作業に伴う排煙・微粒子の飛散
これらは作業員の健康だけでなく、周辺住民への影響も指摘されています。
騒音・振動の発生
クレーン作業やボルト締結時の衝撃音、鉄骨部材同士の接触音などが、住宅地近くではトラブルの原因になりかねません。
鋼材の切断・端材の廃棄
鉄屑や鋼材の端材、使用済み資材は産業廃棄物となり、適正処理が求められます。
業界ではこのような環境課題に対し、さまざまな改善策が模索・実行されています。
近年では、CO₂排出の少ない「電炉鋼材(リサイクル鉄)」が注目されています。廃鉄を再利用して作る電炉鋼材は、環境負荷を大幅に軽減可能です。
鉄骨を工場でユニット化(プレファブ)し、現場ではボルト締結のみで組み上げることで、作業時間と資材ロスを減らす取り組みが増えています。これにより、作業中の騒音や振動も抑制できます。
BIMやドローンによる現場計測・資材配置のシミュレーションにより、過剰な資材手配や輸送回数の削減につながります。
環境対策はゼネコンや施主だけでなく、実際に工事を担う鉄骨業者にも責任がある時代です。
エコマーク付きの鋼材の選定
資材の再利用計画
排出物の記録と適切な廃棄処理
こうした一つ一つの行動が、持続可能な建設業界を支える大切な柱となります。
「強さ」と「柔軟性」を併せ持つ鉄骨構造は、都市を支える基盤です。しかしその強さの裏には環境への代償があることを、私たち業者は自覚しなくてはなりません。
今後の鉄骨工事は、「いかに少ない資源で、最大限の構造をつくれるか」という省資源・省エネの視点が不可欠です。
次回もお楽しみに!
![]()
皆さんこんにちは!
有限会社須永鉄建、更新担当の富山です。
さて今回は
~耐久性~
ということで、、鉄骨建方工事における耐久性の概念、影響を与える要因、具体的な向上策、最新技術の活用について詳しく解説します♪
鉄骨建方工事は、建物の骨組みを形成する重要なプロセスであり、その耐久性は建築物の長寿命化と安全性に直結します。適切な設計、施工、材料の選定、定期的なメンテナンスがなされていなければ、鉄骨の劣化や損傷が進行し、耐震性の低下や事故につながる可能性があります。
鉄骨建方工事における耐久性とは、長期間にわたって建物の構造を支え、安全性を維持する性能を指します。
耐久性が低下すると、以下のようなリスクが発生します。
こうした問題を未然に防ぐために、耐久性を向上させるための対策が必要です。
鉄骨の耐久性に影響を与える主な要因は以下の通りです。
鉄骨は、周囲の環境によって劣化速度が異なります。
| 環境要因 | 影響 |
|---|---|
| 湿度・水分 | 錆・腐食の進行を加速 |
| 温度変化 | 熱膨張・収縮による歪み |
| 化学物質(酸・塩分) | 腐食の進行 |
| 風圧・地震 | 接合部への負担 |
特に、海沿いや工業地帯では塩害・化学腐食が進行しやすいため、特別な対策が必要になります。
耐久性の確保には、施工精度が重要です。
施工精度が低いと、後々のメンテナンスコストが増加するため、適切な施工管理が求められます。
鉄骨の耐久性を維持するためには、定期的な点検と補修が必要です。
| 点検項目 | 内容 |
|---|---|
| 錆・腐食の有無 | 表面の劣化・塗装の剥がれを確認 |
| ボルト・溶接部の確認 | 緩み・亀裂の有無を点検 |
| たわみ・歪みのチェック | 水平・垂直のズレを確認 |
| 耐震補強の確認 | ダンパー・ブレースの状態を点検 |
**超音波探傷検査(UT)や磁粉探傷試験(MT)**を活用することで、目に見えない内部の損傷を検出できます。
近年、鉄骨の耐久性向上に向けた最新技術の導入が進んでいます。
鉄骨建方工事の耐久性を向上させるには、適切な材料の選定・防錆対策・精密な施工・定期点検の実施が不可欠です。
✔ 重要ポイントまとめ
✅ 高耐久な鉄骨・ボルトを使用する
✅ 防錆処理・塗装を徹底する
✅ 正確な施工と溶接管理を行う
✅ IoTや最新技術を活用し、リアルタイムで劣化を監視する
これらの対策を講じることで、鉄骨建方の長寿命化と安全性の向上が実現できます。
次回もお楽しみに!
![]()
皆さんこんにちは!
有限会社須永鉄建、更新担当の富山です。
さて今回は
~組み方~
ということで、鉄骨建方工事の基本的な流れ、組み方のポイント、安全対策、最新技術の活用について詳しく解説します♪
鉄骨建方工事は、建築物の骨組みを形成する重要な工程です。鉄骨の組み方には、安全性・精度・作業効率のすべてを考慮した施工計画が求められます。
鉄骨建方工事とは、建物の鉄骨フレームを組み立てる作業を指します。クレーンを使用して鉄骨を吊り上げ、ボルトや溶接で接合しながら建物の骨格を形成していきます。
この工程は、建物の強度や精度に直接影響するため、適切な手順と技術が求められます。
鉄骨建方の基本的な流れは、以下のようになります。
建方作業の前に、以下の準備を行います。
ブレースは鉄骨構造の耐震性や安定性を確保するための補強材です。
クレーンの位置が悪いと作業効率が低下します。
鉄骨建方工事は高所作業が多く、事故リスクが高いため、安全対策が不可欠です。
| リスク | 対策 |
|---|---|
| 高所作業の転落 | フルハーネス安全帯の使用、足場の設置 |
| クレーン作業時の事故 | 合図者の配置、無線での連携 |
| ボルト締結不良 | 目視確認+トルクレンチによる管理 |
| 強風による鉄骨の揺れ | 風速5m/s以上で作業を一時停止 |
また、朝礼やKY(危険予知)活動を毎日実施し、作業員全員でリスクを共有することが重要です。
近年、鉄骨建方工事ではデジタル技術の活用が進んでいます。
鉄骨建方工事では、正確な施工計画、安全対策、効率的な作業が求められます。
✔ 重要ポイントのまとめ
✅ クレーン配置・作業順序を計画的に決定する
✅ 仮締め・本締めの適切なタイミングを守る
✅ 最新技術(BIM、レーザー測定、ドローン)を活用する
✅ 高所作業の安全管理を徹底する
これらを意識することで、鉄骨建方工事の品質向上と安全確保につながります。今後も技術革新を取り入れながら、安全で効率的な施工を目指しましょう。
次回もお楽しみに!
![]()
皆さんこんにちは!
有限会社須永鉄建、更新担当の富山です。
さて今回は
~鉄則~
ということで、鉄骨工事における「鉄則」を「計画・設計」「材料・品質管理」「組立・施工」「安全管理」「環境対応」の5つの視点から深く掘り下げ、鉄骨工事の成功に不可欠な要素を詳しく解説します♪
鉄骨工事は、高層ビル・橋梁・工場・商業施設などの建設に不可欠な技術です。鉄骨構造は強度・耐久性・施工性に優れている一方で、重量が大きく、現場での精密な作業が求められるため、安全管理や品質管理が極めて重要になります。
鉄骨工事では、施工の精度が建物の耐久性や安全性に直結するため、計画段階での徹底した準備が必須です。
✅ 鉄則:「施工前にBIMや3Dモデルを活用し、鉄骨の配置や接合部を事前検証する」
鉄骨工事には、大きく分けて「S造」「SRC造」「SS(スーパー ストラクチャー)造」などの工法があり、用途によって適切な構造を選定する必要があります。
✅ 鉄則:「建物の特性に応じた適切な鉄骨工法を選定する」
鉄骨工事では、使用する鋼材の種類や加工精度が建物の耐久性に直結します。
✅ 鉄則:「建築基準法・JIS規格に準拠した適正な鋼材を使用する」
✅ 鉄則:「工場加工時の寸法精度を確保し、現場での手直しを最小限に抑える」
鉄骨工事では、部材同士を接合する方法として「溶接」と「高力ボルト接合」があります。
✅ 鉄則:「適切な接合方法を選択し、強度と施工性を両立する」
✅ 鉄則:「ミリ単位の精度管理を徹底し、施工誤差を抑える」
鉄骨工事は高所作業が多いため、墜落や転倒のリスクが高い。
✅ 鉄則:「安全帯・親綱・足場を徹底し、高所作業の安全を確保する」
✅ 鉄則:「鉄骨の揚重計画を策定し、安全なクレーン作業を実施する」
鉄骨はリサイクル可能な建材であり、環境負荷の低減が求められる。
✅ 鉄則:「鉄骨のリユース・リサイクルを推進し、廃棄物を最小限にする」
鉄骨工事は、計画・品質・施工・安全・環境のすべてにおいて厳格な管理が求められる分野です。
✅ 計画段階でBIMを活用し、施工精度を向上
✅ 鋼材の品質管理を徹底し、不適格材を排除
✅ 接合方法を最適化し、耐震性・強度を確保
✅ 安全対策を徹底し、作業員のリスクを最小限に
✅ 環境配慮を進め、持続可能な鉄骨工事を実現
これらの鉄則を守ることで、鉄骨工事の品質と信頼性を確保し、未来の建築技術の発展につなげることができるでしょう。🏗✨
次回もお楽しみに!
![]()
皆さんこんにちは!
有限会社須永鉄建、更新担当の富山です。
さて今回は
~歴史~
ということで、鉄骨工事の歴史とその背景について、技術の進化や社会の変遷とともに詳しく解説します♪
鉄骨工事は、現代建築において欠かせない技術の一つです。高層ビルや橋梁、大規模な工場・倉庫など、強度・耐久性・施工性に優れた構造物を実現するために発展してきた建築技術です。
しかし、鉄骨工事の歴史を振り返ると、古代の鉄の利用から始まり、産業革命を経て近代建築に革命をもたらした鉄骨構造の発展が見えてきます。
鉄の利用は、紀元前3000年頃のメソポタミア文明に遡ります。この時代の鉄は、主に武器や農具として使用されていましたが、建築にはほとんど利用されていませんでした。
中世では、鉄は主に城壁や防衛施設の補強材として使用されました。
しかし、この時代の鉄は高価であり、建築の主要構造として使われることはほとんどなかった。
18世紀後半の産業革命により、鉄の製造技術が大きく進歩しました。
この時期、鉄は建築材料としての可能性を持ち始めたが、まだ鋳鉄(鉄を溶かして鋳型に流し込む方法)が主流であり、十分な強度や柔軟性には欠けていた。
19世紀後半には、鋼鉄(スチール)が登場し、鉄骨構造の発展を大きく後押ししました。
この時期、鉄骨構造の技術が確立され、高層建築や大規模な橋梁に応用されるようになった。
19世紀末には、アメリカ・シカゴやニューヨークで鉄骨を使った超高層ビル(スカイスクレイパー)が登場。
この時期には、**鉄骨とコンクリートを組み合わせた「鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)構造」**が生まれ、耐震性の向上が図られる。
現在の鉄骨工事は、超高層ビルや大規模な建築に欠かせない技術として発展しています。
「ブルジュ・ハリファ」(2010年・ドバイ)
「東京スカイツリー」(2012年・日本)
近年、鉄骨工事は環境負荷の低減と効率化を目指した技術革新が進んでいます。
✅ 古代~中世:鉄は補強材として使用(ローマ帝国・ゴシック建築)。
✅ 産業革命(18世紀~19世紀):鉄骨構造の基盤が確立(アイアンブリッジ・エッフェル塔)。
✅ 20世紀~現代:高層ビル・橋梁建設で鉄骨工事が不可欠に(エンパイア・ステート・ビル・東京スカイツリー)。
✅ 21世紀~未来:スマート建築技術や環境配慮型の鉄骨構造へ進化。
鉄骨工事は、建築技術の進化とともに発展し、今後もさらなる革新が期待される分野です。💡🏗️
次回もお楽しみに!
![]()